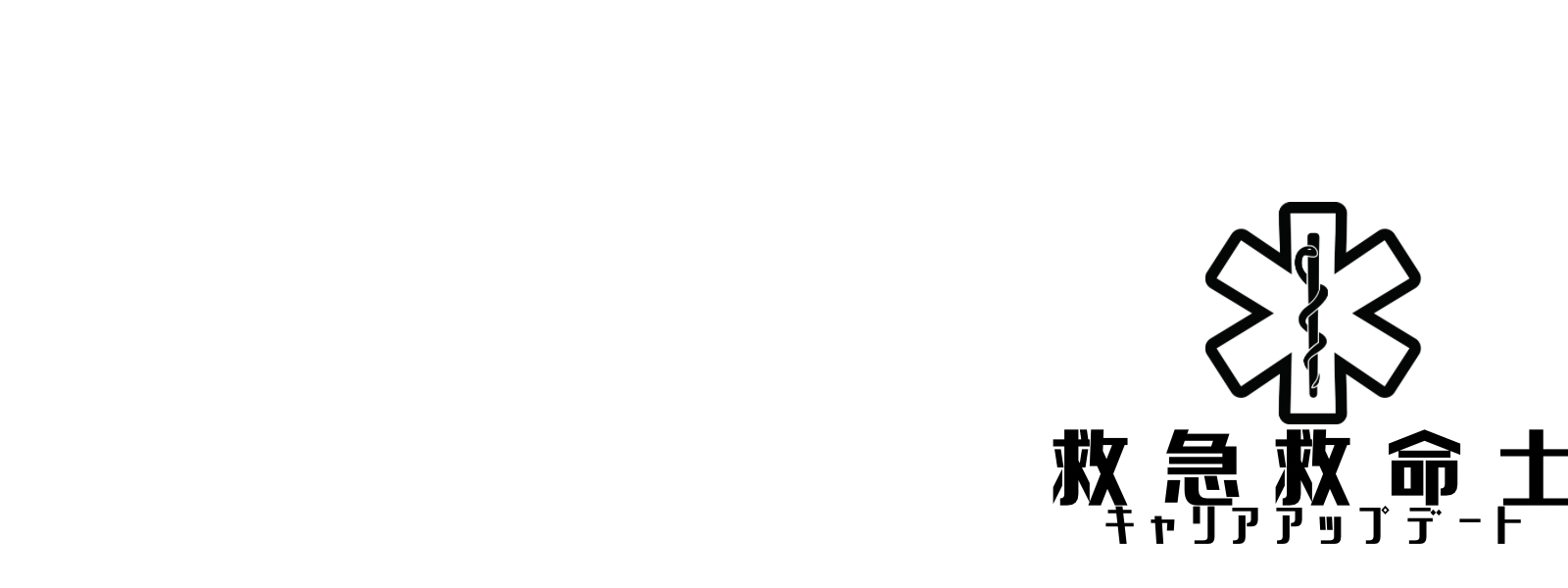- 心拍再開は突発的で総頸動脈触知で判断。
- 総頸動脈の触知 → 呼吸の確認 → 意識の順で初期評価。
- バイタル測定(血圧、心拍数、SpO2値、呼吸数)。
- SpO2値は92〜98%、ETCO2値は35〜45mmHgを目標とし、低酸素血症と高酸素血症を避ける。
- 心拍再開後の4〜6時間は、呼吸や循環動体が非常に不安定。
- 心拍再開後の最大の合併症は再度の「心停止」。
日頃から救急隊は救急活動の訓練を行います。
訓練の内容で「CPA活動」を行いますが、想定がCPAのまま病院搬送、または想定時間が来るまで活動といった内容ではないでしょうか?
CPAのまま隊の活動訓練を行うのも重要です。
しかし、救急隊は傷病者をROSCさせ社会復帰させるのが目標のため、普段からROSC後の活動を取り入れ訓練しなければなりません。
今回はROSC後の救急隊の活動についてまとめました。
救急隊のROSC判断
- 頸動脈が触知可能。
- ROSCを判断するポイントは、リズムチェック、パルスチェック、体動など。
- organized rhythm(オーガイナイズドリズム)と判断した場合、波形、脈を確認。
ROSCとは1分以上の心拍再開のことです。
救急現場では、VF/VTがPEA/Asystoleに変化し、逆もまた珍しくありません。
このように波形が変化していくアルゴリズムをメガコードアルゴリズムと言います。

救急隊がROSCを判断するポイントは、リズムチェック、パルスチェック、体動などです。
以前までは、脈が触れる傷病者に胸骨圧迫を実施するとVF/VTを再発させると考えられていたため、毎回ルーチン化していました。
しかし、現在では心拍がある傷病者に胸骨圧迫を実施してもVF/VTを再発させないとエビデンスが変わりました。

その結果、心拍があるか・ないか分からない場合は胸骨圧迫を実施するべきとなりました。

脈がある・ないより、胸骨圧迫の遅れの方がデメリットが大きいってことだね!
そのため、リズムチェックなどモニターのみでの判断(心拍があるか・ないか)ではなく、心拍がある可能性を瞬時に判断し、可能性がある場合リズムチェックを行うことになりました。
心拍がある可能性の波形とは「QR幅が狭く、R-Rが整」な波形。

QR幅が狭く、R-Rが整な波形のことを「オーガナイズドリズム」と言うよ!

つまり、VF/VT、PEA/Asystole以外だったらリズムチェックだね!
オーガナイズドリズムと判断した場合、波形、脈を確認し触れなければPEAと判断しCPR。触れればROSCと判断。

結論としては、脈が触れる可能性がない波形に対し、リズムチェックを行う必要はないということです。
傷病者のROSC後の救急活動
- 総頸動脈の触知 → 呼吸の確認 → 意識の順で初期評価。
- バイタル測定(血圧、心拍数、SpO2値、呼吸数)。
- SpO2値は92〜98%、ETCO2値は35〜45mmHgを目標とし、低酸素血症と高酸素血症を避ける。
- 原因検索。
AHA蘇生ガイドライン2020版の心拍再開後のアルゴリズムと私の経験則を合わせて解説します。
引用:AHA公認 ACLS BLS講習会福岡博多トレーニングセンター「ACLSとは|ACLSの要点整理|IV、心肺停止」 心拍再開後のアルゴリズム
心拍再開後にすることは「初期評価」。
総頸動脈の触知 → 呼吸の確認 → 意識の順で確認を行います。

その際、循環が40回/分未満であれば再度胸骨圧迫、呼吸がなければ6秒に1回の人工呼吸が必要(意識なし、呼吸なし、脈あり)。
その後、バイタル測定(血圧、心拍数、SpO2値、呼吸数)となります。
人工呼吸をする際に過換気にしてはいけません。
SpO2値は92〜98%、ETCO2値は35〜45mmHgを目標とし、低酸素血症と高酸素血症を避けましょう。

過換気だと、胸腔内圧を上昇させ静脈還流を悪くし、冠灌流圧を 低下させるため蘇生率の低下につながるよ!
蘇生後は血管抵抗が低下しているため、救急隊は輸液を全開に流し、継続的な血圧測定を行います。

高体温を除き保温処置も忘れずに実施。
継続的な初期評価・バイタル測定を実施するとともに、第3者からの詳しい情報も聴取しましょう。
病院ではROSC後、上記に加え原因検索も実施します。(他にもありますがここでは解説なし)
確認できる原因検索を救急隊がすることで、傷病者への根本的治療が早くなる可能性があります。
なので、初期評価・バイタル測定に加え12誘導心電図、身体所見の確認も行いましょう。
心拍再開後の傷病者管理

- 心拍再開後の4〜6時間は、呼吸や循環動体が非常に不安定。
- 心拍再開後の最大の合併症は再度の「心停止」。
- 極端な高酸素血症、低酸素血症、高二酸化炭素血症(低換気)、低二酸化炭素血症(過換気)、低血圧、極端な血圧上昇はいずれもROSC後の重要臓器の回復に必要な代謝を妨げ悪影響。
心拍再開後の4〜6時間は、呼吸や循環動体が非常に不安定であることが広く認知されています。
この不安定な時期の最大の合併症は再度の「心停止」。

心拍が再開した傷病者の最大の死亡原因となってるよ!
極端な高酸素血症、低酸素血症、高二酸化炭素血症(低換気)、低二酸化炭素血症(過換気)、低血圧、極端な血圧上昇はいずれもROSC後の重要臓器の回復に必要な代謝を妨げ悪影響を及ぼします。
| ROSC後の経過に悪影響を及ぼす因子 |
|---|
| 極端な高酸素血症 |
| 低酸素血症 |
| 高二酸化炭素血症(低換気) |
| 低血圧 |
| 極端な血圧上昇 |
| 高体温 |
| 高血糖 |
| 低血糖 |
| 痙攣 |
ROSC後の傷病者は心拍数・血圧は通常以上まで上昇しますが、すぐに低下します。

また、心肺停止後数分以内にROSCすると、直後から自発呼吸が出現し、意識が回復します。
しかし、長時間の心肺停止が続いていると、自発呼吸はすぐには出現しません。
脳への虚血の時間が長ければ長いほど回復は遅れ、遷延性意識障害に陥ります。
主要参考・引用文献
- 第10版 救急救命士標準テキスト「心拍再開後の病態」
- JRC蘇生ガイドライン2020「第2章 二次救命処置(ALS:Advanced Life Support)」
[https://www.jrc-cpr.org/jrc-guideline-2020/],2024年3月10日閲覧