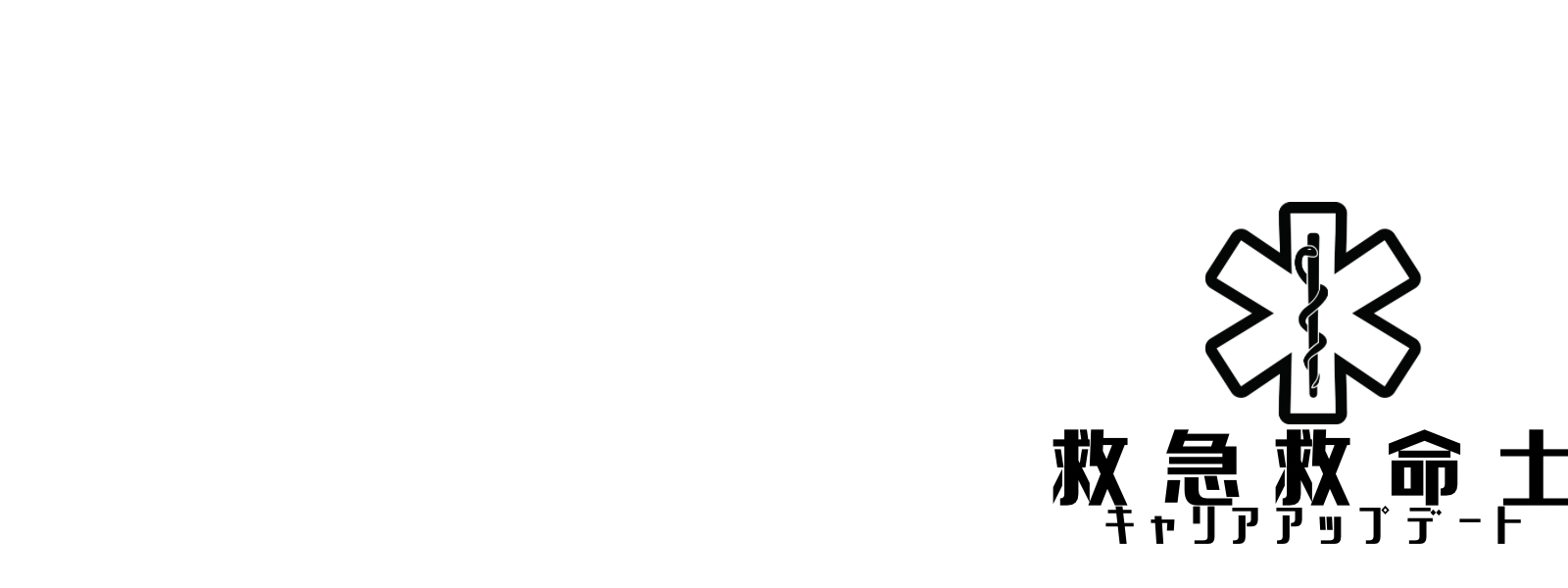- 大動脈解離とは“中膜”が裂ける病気。
- 初動で胸痛・背部痛・胸背部痛 + 突発的、60歳以上、高血圧の既往、冷汗・冷感・嘔気嘔吐のいずれか認めれば強く疑う。
- 問診では発症時刻や発症時何をしていたか答えることができたら“突発的”と判断。
- 痛みの部位、強さ、継続時間を聴取する。
- 痛みは時間経過とともに軽減する。
- 偽腔の部位/狭窄による全身所見を把握する。
大動脈解離の症状を聞くと“血圧の左右差”と思い浮かぶ人が多いのではないでしょうか?
“血圧の左右差” = 大動脈解離の認識だと現場で遭遇したさいに見逃してしまう恐れがあります。文献上でよく目にする“血圧の左右差”の頻度はそれほど高くなく20%以下という報告。
大動脈解離は重症度、緊急度がともに高く、症状も多岐にわたるので症状を理解することは救命率を上げるために必要になります。
私も勉強会で大動脈解離の話を聞いたことがありますが、症状が多岐にわたり覚えるの断念した経験があります。
また、勉強しようにも時間がなくなかなか出来ません。
今回は大動脈解離について現場で見逃し厳禁なポイントや症状をまとめました。
救急隊や救急救命士が現場で大動脈解離を見逃さない、症状のポイントを聞いて疑うことができるよう記事にしています。
ぜひこの機会に“大動脈解離” について理解を深めましょう。
大動脈の理解!

大動脈のポイント!
- 大動脈は大きく“上行大動脈”、“大動脈弓”、“下行大動脈”の3つに分類。
- 大動脈弓からでる3つの血管は“腕頭動脈”、“左総頸動脈”、“左鎖骨下動脈”。
- 血管は“内膜”、“中膜”、“外膜”の3層構造。
大動脈とは、心臓から全身に向かって血液を送り出す際の1番太くて大きい血管になります。
大動脈解離とは、大動脈の中膜という場所が裂ける病気になります。
大動脈解離の種類として、スタンフォードA・B型やドゥベイキーの分類があり、突然の胸背部痛で発症するのが特徴的です。

- 上行大動脈:心臓の入り口から上に向かって走る大動脈。
- 大動脈弓:弓形になっている大動脈。
- 下行大動脈:大動脈弓から下に走る大動脈。

- 腕頭動脈:右腕と右頭に血液を送る動脈。
- 左総頸動脈:左の頭に血液を送る動脈。
- 左鎖骨下動脈:左腕に血液を送る動脈。

動脈の壁は“内膜”、“中膜”、“外膜”の3層構造となってます。
内膜は血管の一番内側を覆い、機能として血管外への物質透過性や血液凝固に関与するほか、血管平滑筋細胞の緊張性、細胞接着・遊送、細胞増殖、炎症作用,血管新生など多くの機能にかかわります。
内皮細胞 の機能障害が起こると血栓症や動脈硬化症の原因となります。
中膜はかなり厚い中間層で、平滑筋と弾性組織で構成。平滑筋は交感神経系の支配を受けており、血管を収縮・拡張させます。それにより血圧は上がったり下 がったり変化します。
外膜は血管の外層で、ほとんど線維性の結合組織からできています。外膜は血管を支持し保護する働きをもちます。

中膜が裂けた場合の血管の断面図になります。
高血圧が解離を起こす理由として、血管の壁にかかる圧力が高くなります。年齢が上がると血管の壁が脆くなり亀裂が入り解離を起こします。
マルファン症候群では先天的に血管の壁(全身の結合組織)が弱いので亀裂が入りやすくなります。
大動脈解離とはどんな病気?

大動脈解離とは?
- 大動脈解離とは中膜が裂ける病気。
- 上行大動脈の解離では胸痛、下行大動脈の解離では背部痛での発症が多い。
- 大動脈解離は“スタンフォードA型”、“スタンフォードB型”に分類される。
- 解離した部位により症状が異なる。
大動脈解離とは中膜が裂ける病気になります。大動脈解離の多くは動脈硬化を基礎に発症。
上行大動脈から始まる解離は胸痛で、下行大動脈から始まるものは背部痛で発症することが多いと言われます。
典型的には解離に伴う激しい痛みが主症状ですが、中には無痛性の大動脈解離を発症している傷病者もいるので注意が必要。
大動脈解離は治療方針を反映するスタンフォード分類があります。

- スタンフォードA型:解離が上行大動脈に及んでいるものをA型。痛みの始まりは全胸部痛。
- スタンフォードB型:解離が鎖骨下動脈分岐以下の下行大動脈にとどまるものをB型。痛みの始まりは肩甲骨の間付近から。
大動脈解離は解離の部位により多彩な症状が出現します。

大動脈起始部の病変では、心タンポナーデや冠動脈閉塞による心筋梗塞。
弁輪が変形し大動脈弁閉鎖不全症を生じれば急性左心不全。
大動脈弓に解離が生じると、腕頭動脈や左総頸動脈の閉塞により意識障害や片麻痺などの脳卒中症状。
胸腔内、縦隔内、後腹膜内へ破裂すると出血性ショックを呈する。

血圧の左右差は20%以下、脈拍消失は15%に見られるよ!

大動脈解離が起こると血管が拡張し大動脈弁の動きを邪魔します。結果、大動脈弁が閉じれなくなり血液が逆流し、心臓に血液が溜まります。
左心室のポンプ機能が低下し肺静脈に血液が溜まり、肺にも血液が溜まるようになります。これが呼吸困難を引き起こし肺水腫という症状になります。→ 左心不全
大動脈解離は解離の部位により様々な症状を呈します。救急隊はオーバートリアージだけではなく、ワイドトリアージも実施し、常にさまざまな疾患を疑いましょう。
救急隊の現場活動

突然発症の胸背部痛、移動する痛みなどの典型的な症状があれば大動脈解離を疑うことは難しくありません。
しかし、実際の現場はそうではありません。上記の特徴的な症状がなかったり、意識障害が先行し情報を聴取できなかったりします。
現場では、意識障害や胸痛、麻痺、心タンポナーデなどの症状を確認したらセットで大動脈解離も念頭において活動しましょう。
初動で大動脈解離を強く疑う初見
- 突発的な胸痛・背部痛・胸背部痛
- 60歳以上の胸痛・背部痛・胸背部痛
- 高血圧既往のある胸痛・背部痛・胸背部痛
- 冷汗、冷感、嘔気、嘔吐を伴う胸痛・背部痛・胸背部痛
上記にいずれかに加え、「麻痺症状」、「血圧の左右差」、「痛みの移動」、「頸静脈怒張」を認めれば“スタンフォードA型”を疑いましょう。
大動脈解離を疑った救急隊の問診のポイント
- 発症時刻(時間や何をしていたか正確に答えることができたら突発的と判断)
- 痛みの部位
- 痛みの強さ(最大を10)
- 痛みの持続時間
全身初見(偽腔の圧迫/狭窄による部位別症状)
- 腕頭動脈・左総頸動脈狭窄
- 脳虚血→目眩・頭痛・失神・意識障害・痙攣
- 頸動脈洞反射亢進(後部後屈時)→血圧低下
- 眼動脈高血圧性変化→眼底出血、白斑
- 鎖骨下動脈狭窄
- 上肢脈拍に左右差、上肢・下肢の左右差(上肢<下肢)、上肢麻痺
- 冠動脈狭窄
- 心筋梗塞(冠動脈入口部《バルサバ洞》の閉塞)
- 上行大動脈狭窄
- 拡張による弁輪拡大→大動脈弁閉鎖不全症→心不全
- 冠動脈起始部狭窄→狭心症、心筋梗塞
- 下行大動脈狭窄
- 血圧の上下差(上肢>下肢)
- 肋間動脈狭窄
- 対麻痺
- 腹腔動脈狭窄
- 肝不全、胃潰瘍
- 腎動脈狭窄
- 腎不全
- 上下腸管膜動脈狭窄
- 腹痛、腸麻痺、便秘、潰瘍
- 下肢動脈狭窄
- 下肢脈拍減弱、間欠性跛行
引用:石川県救急活動プロトコル
最後に注意が必要な所見として、大動脈起始部からの解離だと冠動脈に血液が行かず“徐脈”を認める場合があるので見逃さないよう注意しましょう。

解離の痛みで脈拍上昇、血圧上昇だけじゃないんだね!上記では脈拍低下、ショックだと血圧低下または両方の低下が見られるね!
大動脈解離の危険因子
- 高血圧
- 脂質異常
- 糖尿病
- 喫煙
参考:「第10版 救急救命士標準テキスト」「石川県救急活動プロトコル」「J–STAGE/大動脈瘤および大動脈解離の病理」