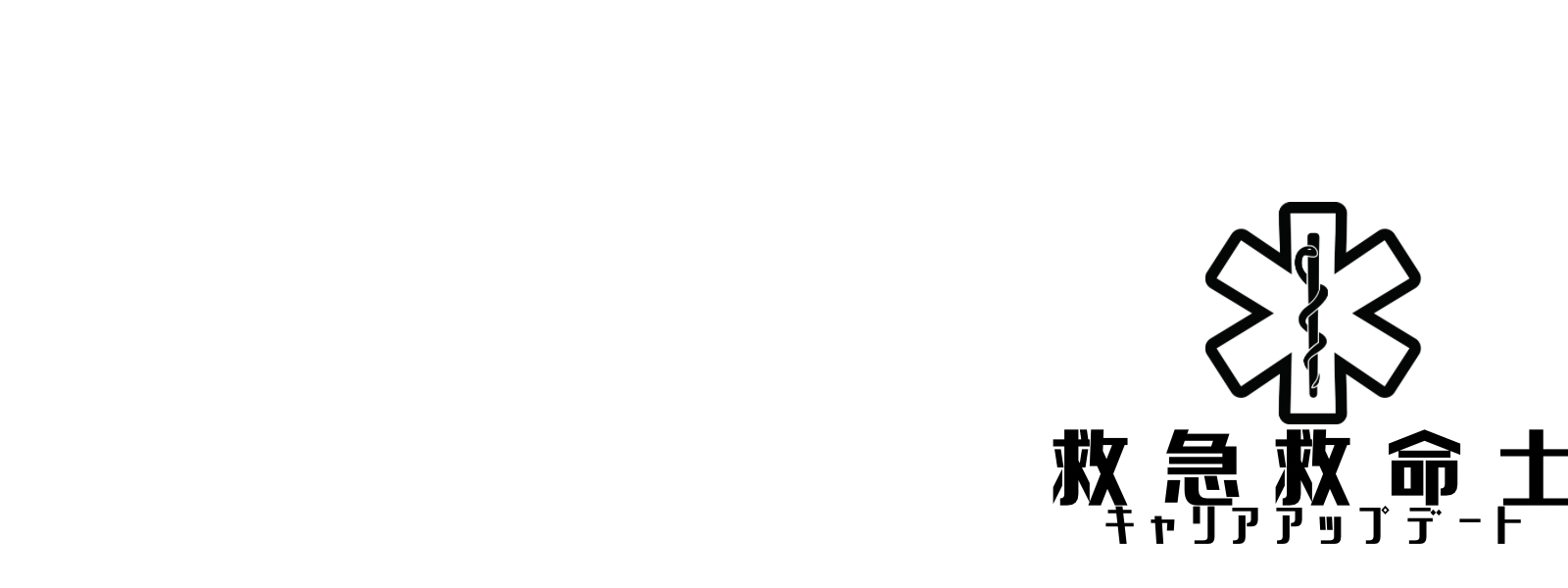- 血管の選定は “触れて見える血管” > “触れる血管” > “見える”の順番。
- Y字、真っ直ぐで長い血管は穿刺しやすい。
- IV確保時のテンションは血管の横。
- 留置針はゲージ数によって長さ太さが違う。
- 留置針は商品によって逆血の方法は異なる。
- IV確保時は隊員の補助が必須。
J-STAGEによると、CPA時の静脈路確保の成功率は58.5%という結果でした。(以下IV確保と記載)
救急救命士が行うIV確保は現場や救急車内での実施となり、成功させるのはかなり難しいと思います。
私も揺れる車内での実施や畑など様々な場所で実施してきましたが、成功率が90%を超えるのに数年はかかりました。IV確保は、CPAの傷病者や重篤なショックの傷病者にとって重要な処置です。
IV確保をどう成功に導けるかで、処置の幅や活動のクオリティが決まってきます。
あくまで私の考えではありますが、IV確保を成功に導ける要因として①血管の選定、②留置針の理解、③隊員の補助の3点がとても重要だと思います。
今回はIV確保をどうしたら成功に導けるか、私の経験や勉強してきた内容を記事にしたいと思います。
IV確保の成功率が低く訓練や勉強をし踠いている人は、一度立ち止まって読んでほしい内容になっています。
IV確保時の血管選定のコツ!

IV確保時に選ぶ血管
- 見えて触れる血管
- 触れる血管
- 真っ直ぐ走行している血管
- Y字に走行している血管
IV確保を成功させる1番の要因として血管の選定にあります。救急救命士が穿刺できる血管が、「手背静脈」「橈側皮静脈」「尺側皮静脈」「肘正中皮静脈」「大伏在静脈」「足背静脈」の6箇所。
上記で挙げた血管であればどれでもいいと思っている間は成功率は上がりません。
重要なのは“見えて触れる血管”、あるいは“触れる血管”を選定することです。逆に失敗する血管としては“見える血管”があります。
では、“見えて触れる血管”、“触れる血管”がどうしていいのか写真と一緒に解説したいと思います。
“見える”血管よりも“触れる”血管

皮膚表面を走行している青っぽく視認することができる血管は失敗しやすくなります。十分な内径と壁の厚みがあり穿刺時に突き破りにくい血管は“触れる”血管。
現場でIV確保する優先順位の高い血管として。“見えて触れる血管” > “触れる血管” > “見える血管”の順になります。

“見える”だけの血管は脆弱で失敗するリスクが高くなるよ!

また、穿刺しやすい血管として、蛇行していない真っ直ぐな血管とY字走行があります。
Y字走行であれば血管の合流地点めがけて穿刺することで成功率が高くなります。真っ直ぐ走行している血管は説明するまでもなく皆さん選択していると思います。
真っ直ぐな血管に関しては使用する針の長さ分あれば大丈夫です。
IV確保時のテンションのかけ方!

では、実際に穿刺をする前のテンションをかける指の位置はどうしたらいいでしょう?

血管の横からテンションをかけた場合、真っ直ぐ走行している血管をしっかり確認することができます。

血管の上からテンションをかけた場合、真っ直ぐ走行してる血管が途中から視認しづらくなったのがわかると思います。
このように血管の上からテンションをかけてしまうと、環流が途絶えてしまい視認しづらくなるほか、血管上に指があるため穿刺の邪魔になり、穿刺する幅を狭める原因にもなります。
IV確保で使用する留置針の理解!

留置針の特性!
- 内筒が血管に入ることで外筒に血液が流れるタイプ。
- 外筒が血管に入ることで外筒に逆血が流れるタイプ。
- 留置針の外筒に止血弁があるタイプ。
穿刺をする場合、「穿刺」→「逆血確認」→「寝かせて1〜2mm挿入」→「外筒挿入」→…と習ったと思います。
しかし、この流れは使用する留置針によって変わってきます。救急隊が使用する留置針は「18G」「20G」「22G」「24G」となっています。
- 18G:外針(カテーテル長) 32mm
- 20G:外針(カテーテル長) 32mm
- 22G:外針(カテーテル長) 25mm
- 24G:外針(カテーテル長) 19mm

18Gの針であれば、血管を直接狙う場合はある程度の長さが必要になります。逆に24Gだと直接血管を狙わないと、針が短く到達できな可能性が出てきます。
メーカーや商品によって長さは異なりますが、ここで重要なことは使用する留置針の特性を理解するということです。
次に逆血についてです。逆血は穿刺する際に針が血管に入ったと判断する際に重要です。しかし、逆血の確認方法にも種類があることを知っていましたか?
①の場合、内筒が血管に入ることで外筒に血液が流れるタイプの留置針になります。
②の場合、外筒が血管に入ることで外筒に逆血が流れるタイプになります。

つまり、①の場合は逆血が確認できたら、寝かせて進める操作が必要になります。しかし、②の場合は逆血があったタイミングで外筒を進めても問題ないということです。
②は寝かせて進める操作が無駄であり、血管を突き破るリスクがあるので、その操作をする際は注意が必要になります。
留置針には止血弁がある商品もあります。内筒を抜いた後、逆手による血管の圧迫が必要ないため、救急救命士の負担が減ります。
当ブログで紹介した留置針だけでも特性が様々で、商品によってはさらに異なる点が多数あるでしょう。自分たちが保有している資機材を把握することも成功要因の1つと言えます。

留置針のパッケージにはさらに有用な情報があるね!滴下速度だったり針の太さだったり!
隊員の補助!

最後に隊員補助についてです。救急救命士が穿刺するタイミングで救急車を減速し、揺れを少なくすることでかなり助かります。
また、用手での胸骨圧迫の際はちょっとズレてスペースを作ってあげることで、穿刺がしやすくなります。
血管の走行によっては、胸骨圧迫やルーカスの圧迫の振動が傷病者にも伝わってしまうこともあります。(狭隘な空間の場合、上肢が機械やCPR実施者に密着するため)
その場合、CCFは下がりますが2秒〜3秒停止し穿刺できるタイミングを作ってくれることも成功できる要因になります。
救急救命士がIV確保を成功できるかは、救急救命士の腕以外にも隊員の協力やIV確保できる環境づくりも重要です。

針の固定テープ準備や活動から外れてIV確保の準備させてくれるのも助かるね!
最後に
今回、IV確保の成功率を上げるための方法を紹介しました。これが全てではなく 1人1人自分なりのやり方があると思います。
この方法だけが正しいわけではなく、正解は無数にありあるので、当記事は参考にと思ってください。ただ、IV確保で行き詰まっている人はぜひこの方法を実践に移してください。
また、所属や地域、MC、使用しいる商品によって活動内容など異なります。前述したとおりそちらを優先して活動しましょう。