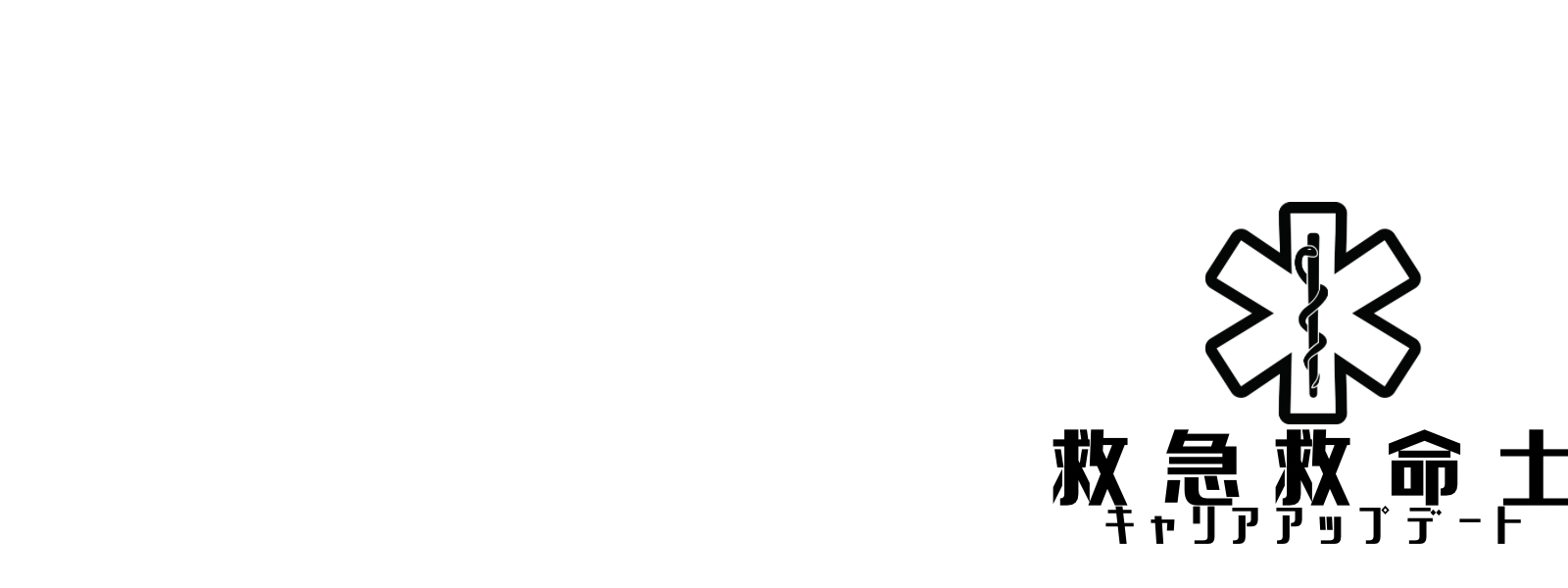- 気道異物の症状には、突然のむせ込みや咳き込み、喘鳴や呼吸困難、顔色の青白さや紫色化、意識障害や心停止などがある。
- 気道異物で窒息した場合は、119番通報と異物除去を行う。
- 窒息している場合は背中をたたく(背部叩打法)や上腹部を圧迫する(腹部突き上げ法)。
- 不完全窒息の場合はできるだけ咳を続けさせる。
- 腹部突き上げ法を行った場合は内臓損傷の可能性があるため、必ず病院受診。
気道異物による窒息は、子どもだけでなく大人にも起こりうる危険な状況です。
目撃者やその場に居合わせた人が適切な処置を行うことで、命を救うことができます。
この記事では、気道異物の原因や症状、応急処置の方法、予防法などについてまとめました。
気道異物とは?原因や症状を知ろう
- 気道異物の症状には、突然のむせ込みや咳き込み、喘鳴や呼吸困難、顔色の青白さや紫色化、意識障害や心停止などがある。
- チョークサインは万国共通の気道異物のポーズ。
気道異物とは、食べ物や小さな物体が誤って気道に入り込んで空気の通り道を塞いでしまうことです。
原因には、食べ物(ピーナッツや枝豆、餅など)、魚の骨、ビニールやプラスチックなどの玩具の部品、乳歯、痰の塊など口に入るもの全てとなります。
気道異物の症状には、突然のむせ込みや咳き込み、喘鳴や呼吸困難、顔色の青白さや紫色化、意識障害や心停止などがあります。

下の写真は「チョークサイン」と言いって、万国交通の窒息しているポーズだよ!

気道異物は子どもに多く見られますが、大人でも起こり得ます。
特に高齢者や認知症、嚥下障害のある人は注意が必要。
気道異物で窒息したら?応急処置の方法を覚えよう
- 気道異物で窒息した場合は、119番通報と異物除去を行う。
- 窒息している場合は背中をたたく(背部叩打法)や上腹部を圧迫する(腹部突き上げ法)。
- 不完全窒息の場合は「ゼーゼー」、「ヒューヒュー」など異常な呼吸。
- 不完全窒息の場合はできるだけ咳を続けさせます。強い咳により自力で排出できることがある。
- 腹部突き上げ法を行った場合は内臓損傷の可能性があるため、必ず病院受診。
完全に窒息した場合
呼びかけに対して、声が出せない、またはチョークサインを示している場合には気道異物の可能性があります。
気道異物で窒息した場合は、119番通報と異物除去を行いましょう。
意識がある場合は、背中をたたく(背部叩打法)や上腹部を圧迫する(腹部突き上げ法)で異物を排出させます。


上記処置を行っても異物が取れず意識が無くなった場合は、心肺蘇生法(胸骨圧迫と人工呼吸)を行い、AEDがあれば使用。
応急処置中に異物が見えたら取り除きます。
また、腹部突き上げ法を行った場合は内臓損傷の可能性があるため、必ず(異物が取れた場合も)病院受診しましょう。

実施手順にあっては東京消防庁公式チャンネルを参考にしてね!
東京消防庁「窒息に対する応急手当(成人:背部叩打法)」
東京消防庁「窒息に対する応急手当(小児・成人:腹部突き上げ法)」
東京消防庁「窒息に対する応急手当(乳児:背部叩打法)」
東京消防庁「窒息対する応急手当(乳児:胸部突き上げ法)」
不完全な窒息
不完全な窒息とは、気道に異物があるもかろうじて呼吸ができる状態。
呼吸ができていいるものの「ゼーゼー」、「ヒューヒュー」など異常な呼吸をしています。
このように異常な呼吸音がする場合には、本人に咳をさせましょう。
できるだけ咳を続けさせます。強い咳により自力で排出できる場合があります。
気道異物の予防は?子どものそばに危険なものを置かない
- 子どもが誤嚥してしまう大きさかどうかを調べる方法は、トイレットペーパーの芯を半分に切って、そこに入るかどうかを見る。
- 子供の手の届く範囲に物を置かない。
気道異物の予防のためには、家族全員が協力する必要があります。
子どもが誤嚥してしまう大きさかどうかを調べる方法は、トイレットペーパーの芯を半分に切って、そこに入るかどうかを見るとわかりやすいです。
政府広報オンライン「えっ?そんな小さいもので?子供の窒息事故を防ぐ!」
また,子供の目線で物が落ちてないか探すことで、未然に防ぐことができます。
子どもの手の届かないところに危険なものを置かないようにしましょう。
政府広報オンライン「えっ?そんな小さいもので?子供の窒息事故を防ぐ!」
高齢者や嚥下障害のある人は、食事の形態や量を調整しましょう。
主要引用・参考文献
- 第10版 救急救命士標準テキスト「異物」,2023年9月9日閲覧
- 日本医師会「救急蘇生法/気道異物の除去の手順」
[https://www.med.or.jp/99/kido.html],2023年9月9日閲覧 - 政府広報オンライン「えっ?そんな小さいもので?子供の窒息事故を防ぐ!」
[https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201809/2.html],2023年9月9日閲覧