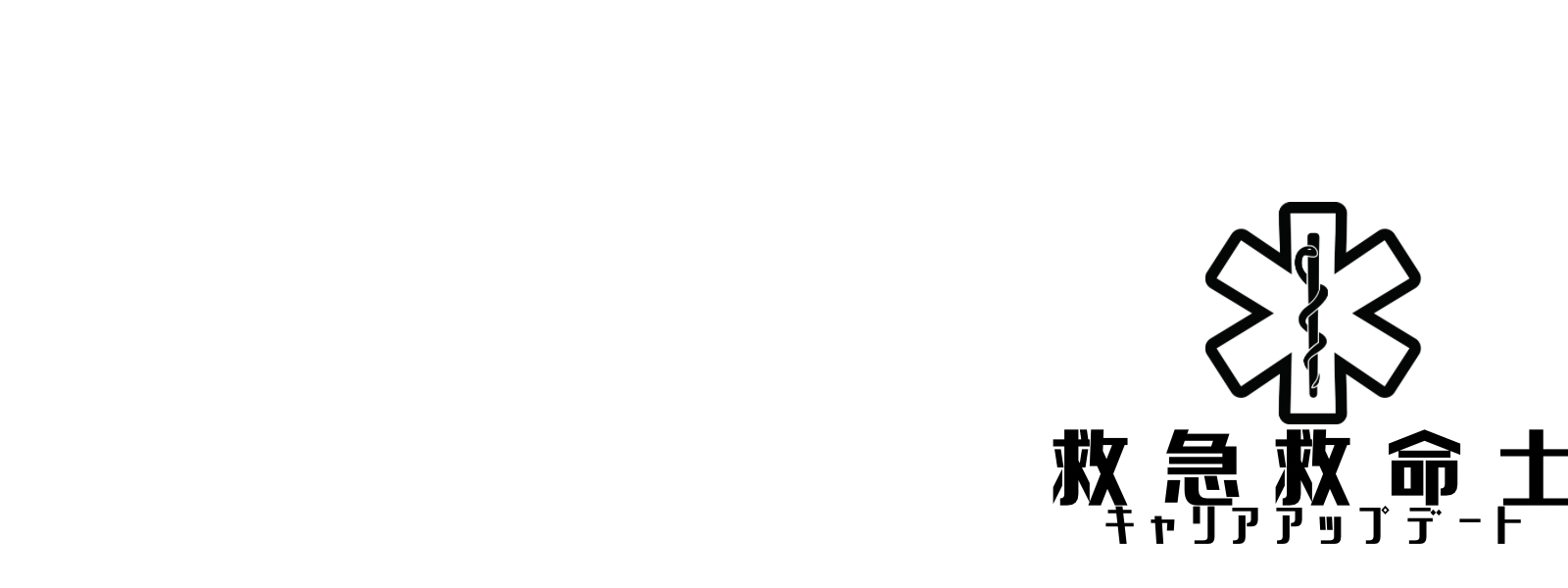- 小児の初期評価は第一印象で行う。
- 観察には保護者の協力が不可欠。
- 「AVPU」「TICLS」「小児GCS」を活用。
小児救急でよく困ることは、現病・既往がない場合が多く、訴えが乏しいことです。
実際に救急現場に行った際にも、「小児 痙攣している」などの内容であれば、まだ観察しやすいです。

「発熱」「失神」「下痢」などキーワードが1つしかいない場合苦慮するね!

私も小児の観察は苦手!成人と比べて訴えがなく、バイタルも正常を覚えにくい!
今回は小児の観察のポイントについてまとめています。
小児の救急が苦手な人はぜひ参考にてして現場に活かしてください。
小児の初期評価は第一印象
- 小児の初期評価は第一印象で行う。
- 観察には保護者の協力が不可欠。
- 年齢にあった反応を確認する。
小児の初期評価をする上で大切なポイントは第一印象になります。
ここでの第一印象とは、意識や顔貌、呼吸状態、筋緊張などを指します。

| Emergency 致死的状態や四肢の損失、その状態に陥りそうな | Sick 致死的状態になる可能性 四肢機能損失の可能性 医療介入が必要な状態 | |
|---|---|---|
| 外観 | ・昏睡 ・痛み刺激に無反応 ・痙攣中 | ・傾眠、混迷、混乱 ・痙攣頓挫後の意識障害 ・意識障害を疑う |
| 呼吸 | ・呼吸停止/呼吸不全、高度徐呼吸 ・発語、会話不能 ・アナフィラキシー ・上気道症状:窒息、著名な流涎、陥没呼吸、喘鳴 ・下気道症状:呼吸不全 | ・呼吸促迫症状が明らか(会話困難、多呼吸、努力呼吸、呻吟、鼻翼呼吸、陥没呼吸、肩呼吸) ・上気道閉塞:吸気性喘鳴 ・下気道閉塞:呼気性喘鳴 |
| 循環 | ・心停止 ・重篤な臓器灌流障害、ショック ・大量出血 | ・末梢循環不全(末梢冷感、チアノーゼ) ・強度の痛み(苦悶様顔貌、発汗) ・大量出血 |
上記の内容を評価することで、酸素化の状態や脳血流など体が正常に保たれているのかどうかを瞬時に判断できます。
外観の評価項目として「TICLS」を用います。
| 評価 項目 | 正常 所見 | 異常 所見 |
|---|---|---|
| Tone:筋緊張 | ・適度な筋緊張 ・均等な四肢の動き ・元気に動いている | ・流涎 ・筋肉の硬直 ・ぐったりしている |
| Interactiveness:周囲への反応 ・受け答えの様子 ・保護者とのやり取り ・医療者への反応 | ・年相応の呼名反応 ・周囲への関心(人・物・音で注意を逸らす。または注意を引く) | ・反応が乏しい ・保護者を認識できていない ・無関心 |
| Consolability:精神的安定 ・保護者や医療者にあやされたり、 宥められたりした時の様子 | ・あやされたり、なだめると落ち着く | ・なだめても泣き止まない ・興奮 ・抱いている時は不機嫌、そうでない時はぐったり |
| Look/Gaze:視線/注視 | ・開眼 ・視線が定まっている | ・うつろ ・視線が定まらない |
| Speach/Cry:会話/啼泣 話し方 泣き方 | ・力強い啼泣 | ・弱々しい泣き方 ・こもった声や、かすれた声 |

母(父)親に普段とどう違うが聞くとすぐ分かるね!
上記全てを観察するためには保護者の協力が不可欠です。
保護者に児を呼びかけてもらい、反応を確認しましょう。
また、夜間の救急だと眠っているのか意識障害なのか区別がつかない場合があります。
その際は、評価をするために起こすことも重要です。

寝ている所を起こすと泣いてしまって観察しづらいけど、それも評価だね!
小児の発達年齢と行動評価についてまとめた表が以下になります。
| 発達年齢 | 行動特徴 |
|---|---|
| 新生児 | ・原始反射のみ |
| 2ヶ月未満 (乳児) | ・生理的応答 ・分離不安なし |
| 2〜6ヶ月 (乳児) | ・社会性(笑顔、追視) ・運動発達(寝返り、坐位、手を伸ばす) ・発声 |
| 6〜12ヶ月 (乳児) | ・社会性(相互的な行動、人見知り、分離不安) ・補助なしでの坐位を保つ ・遊ぶ、喃語 |
| 1〜3歳 (幼児) | ・恐れを知らない好奇心 ・強い自己主張、非論理的 ・自己中心的 ・人見知り分離不安 ・幅広い言語の変化 |
| 3〜6歳 (幼児) | ・非現実的で非論理的な思考 ・内科系疾患や外相についての論理的だが誤った理解 ・怪我、制御を失うこと、死、暗闇、1人になることへの恐れ ・高い会話能力 |
| 6〜12歳 (学童) | ・口数が多い、分析的である ・理由と影響を理解している ・自分の治療に対して自分で関わることを求める ・分離、制御、痛み、身体的障害への恐れ |
小児の正常バイタル
- 呼吸数は年齢を重ねるごとに減少。
- 脈拍も同様に年齢を重ねるごとに減少。
- 血圧は6歳前後で成人と同様(「70+2×年齢」mmHg)。
- 意識の評価方法は、AVPU評価スケール、小児GCSを推奨。
小児の呼吸
乳児の胸郭は未発達のため腹式呼吸、幼児期から胸式呼吸が加わります。
呼吸数は年齢を重ねるごとに減少。
- 呼吸の正常値
- 新生児:40〜60回/分
- 乳 児:30〜45回/分
- 3歳:25回/分
- 6歳:20回/分
- 12歳:15回/分
小児の脈拍
脈拍も同様に年齢を重ねるごとに減少。
思春期で成人と同様になります。
- 脈拍の正常値
- 新生児:90〜120回/分
- 1歳まで:80〜120回/分
- 3歳まで:70〜100回/分
- 6歳まで:65〜100回/分
- 12歳まで:60〜95回/分
小児の血圧
血圧は6歳前後で成人と同様になると言われています。
- 収縮期血圧(SBP)の最低値
- 0歳児:60mmHg
- 1歳:80〜100mmHg
- 3歳:90〜105mmHg
あるいは、「70+2×年齢」mmHgとされています。
小児の意識レベルの評価
小児の意識レベルの簡易的な評価法として「AVPU評価スケール」を用います。
| 分類 | 刺激 | 適切な応答 | 不適切な応答 |
|---|---|---|---|
| Alert:覚醒 | 普通の環境: 目覚めており、活動的で、周囲の環境の刺激に合目的に反応 | 年齢相応の反応 | |
| Verbal:言葉刺激に反応 | 簡単な指示または音の刺激にだけ反応 | 名前に反応 | 非特異的または錯乱 |
| Painful:痛み刺激に反応 | (胸骨正中・爪床)痛み刺激にだけ反応 | 痛みから逃れようとする | 非合目的か痛みの局在と関係のない発声や動き |
| Unresponsive:反応がない | どのような刺激に対しても検出可能な反応なし | 病的な姿勢をとる |
この評価方法は4段階で評価し、V(Verbal:言葉刺激に反応)、P(Painful:痛み刺激への反応)、U(Unresponsive:反応なし)であれば異常と判断。
特に、P(Painful:痛み刺激への反応)、U(Unresponsive:反応なし)は緊急的な処置が必要であると判断。
小児の意識レベルの評価方法として、JCS、小児GCS、坂本法などありますが、ここでは小児GCSの活用をすすめています。

JCSでは小児の意識レベルと評価が上手くマッチせず、坂本法は乳児のみを対象としており、環境や状況で乳児の機嫌で評価が変わるから使いづらい!
小児GCSであれば、客観的に判断でき小児全て当てはまるため推奨しています。



救急隊の活動
- ABCDEの5項目で評価。
- 意識レベルがGCS合計13点以下、JCS30以上を緊急度が高い目安。
- 意識レベルがGCS合計8点以下、JCS100以上、もしくは呼吸数、心拍数の著しい増加または減少がある場合はより緊急度が高い。
小児の重症度、緊急度を判断するためにはバイタルサインが必須です。
心拍数の年齢別正常値とSD(標準偏差)値および呼吸数の年齢別正常値とSD値を元に評価しましょう。
引用:救急救命士標準テキスト
基本的な評価として、A(気道)、B(呼吸)、C(循環)、D(神経学的所見)、E(全身観察:皮疹や外傷痕、低体温など)の5項目を用います。
意識レベルがGCS合計13点以下、JCS30以上を緊急度が高い目安とします。
また、意識レベルがGCS合計8点以下、JCS100以上、もしくは呼吸数、心拍数の著しい増加または減少がある場合はより緊急度が高いと判断しましょう。
酸素投与を行う場合は、母(父)親に抱き抱えてもらい酸素投与をすることでスムーズに行えます。
搬送医療機関は小児専門医が常駐している医療機関を選定しましょう(CPAなど重症度・緊急度が高い場合はこの限りではない)。
主要参考・引用文献
- 第10版 救急救命士標準テキスト「小児に特有な疾患」
- トリアージナースガイドブック2020「トリアージのプロセス」